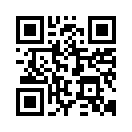2023/06/29
梅雨の晴れ間の2日間、快ラボふくしまが無事終了しました。
24日は症例検討会、25日は保養相談会、快医学入門と体験会、
映画上映(かくれキニシタン)、そして会を盛り上げてくれた
マルシェやライブなど盛りだくさんの内容でした。
一般来場者は200名を超え、スタッフ関係者を含めると
250名以上が集い、それぞれのプログラムを通して
新たな出会いと再会の場になっていました。
東日本大震災・原発事故後から今年で12年目を迎えます。
大きな災害は、私たちに正確な情報と対処の智慧、
それらを共有するコミュニティーと助け合いのセーフティネットが
必要であることを教えてくれました。
「快ラボ・ふくしま」はその活動を担う位置付けとして
企画しましたが、当初の目標は達成できたと考えています。
企画段階から積極的に準備に関わってくれた
快医学講座受講者のみなさん、
テント、会場の設営など縁の下から支えていた
NPO法人ライフケアのみなさん、
快く会場の提供、進行すべてに全面的に協力していただいた
銀河のほとりの克子さんはじめスタッフのみなさん、
講座の進行を担ってくれた
NPO法人快医学ネットワークのみなさん、
暑い中でマルシェに出店していただいた皆さん、
そして会の活動に賛同し、協賛していただいた
個人、団体のみなさんにこころから感謝申し上げます。
すでに来年も開催との声が聞こえてきますが、
ひとまずからだを休め、考えていきましょう。
お疲れさまでした。

24日は症例検討会、25日は保養相談会、快医学入門と体験会、
映画上映(かくれキニシタン)、そして会を盛り上げてくれた
マルシェやライブなど盛りだくさんの内容でした。
一般来場者は200名を超え、スタッフ関係者を含めると
250名以上が集い、それぞれのプログラムを通して
新たな出会いと再会の場になっていました。
東日本大震災・原発事故後から今年で12年目を迎えます。
大きな災害は、私たちに正確な情報と対処の智慧、
それらを共有するコミュニティーと助け合いのセーフティネットが
必要であることを教えてくれました。
「快ラボ・ふくしま」はその活動を担う位置付けとして
企画しましたが、当初の目標は達成できたと考えています。
企画段階から積極的に準備に関わってくれた
快医学講座受講者のみなさん、
テント、会場の設営など縁の下から支えていた
NPO法人ライフケアのみなさん、
快く会場の提供、進行すべてに全面的に協力していただいた
銀河のほとりの克子さんはじめスタッフのみなさん、
講座の進行を担ってくれた
NPO法人快医学ネットワークのみなさん、
暑い中でマルシェに出店していただいた皆さん、
そして会の活動に賛同し、協賛していただいた
個人、団体のみなさんにこころから感謝申し上げます。
すでに来年も開催との声が聞こえてきますが、
ひとまずからだを休め、考えていきましょう。
お疲れさまでした。


2023/06/13
今回の福島・快医学30時間講座での一幕。
大規模災害時などでもしかしたら屋外で
数日間過ごすこともあるかもしれないし、
水害の被害で身体が冷えてしまうこともあるだろう。
深部体温が低下すると、初期症状として体が激しく震える。
これは筋肉を小刻みに動かし筋肉から熱を発生させて体温を
維持しようとする生理現象だが、
さらに体温が低下すると震えが収まり、
動作が遅くてぎこちない、反応に時間がかかる、
思考がぼんやりする、判断力が低くなるなどの症状が現れる。
やがて昏睡状態に陥って、心臓の心拍や呼吸が遅く弱くなり、
最終的には心臓が止まってしまうことも考えられる。
とにかくブルーシート、アルミシート、毛布など
あるもので何重にも包んで保温する。
そしてできるだけ早く医療機関に搬送することが必要だ。
そこで質問です。
現場では2つ飲み物があったとします。
まずどちらを飲ませますか?
①あたたかい番茶
②冷えたコカコーラ(砂糖入り) 表示を縮小

大規模災害時などでもしかしたら屋外で
数日間過ごすこともあるかもしれないし、
水害の被害で身体が冷えてしまうこともあるだろう。
深部体温が低下すると、初期症状として体が激しく震える。
これは筋肉を小刻みに動かし筋肉から熱を発生させて体温を
維持しようとする生理現象だが、
さらに体温が低下すると震えが収まり、
動作が遅くてぎこちない、反応に時間がかかる、
思考がぼんやりする、判断力が低くなるなどの症状が現れる。
やがて昏睡状態に陥って、心臓の心拍や呼吸が遅く弱くなり、
最終的には心臓が止まってしまうことも考えられる。
とにかくブルーシート、アルミシート、毛布など
あるもので何重にも包んで保温する。
そしてできるだけ早く医療機関に搬送することが必要だ。
そこで質問です。
現場では2つ飲み物があったとします。
まずどちらを飲ませますか?
①あたたかい番茶
②冷えたコカコーラ(砂糖入り) 表示を縮小

2023/06/06
ヒトが作っているエネルギーは糖質を使う解糖系、
タンパク質、脂質を使うミトコンドリア系の
2つの作り出す仕組みがある。
ジャンクフード、精白穀物、砂糖などの大量摂取は、
ミトコンドリアでのエネルギー産生が十分行われず、
代謝産物の二酸化炭素を感知する大動脈センサーが作動しない。
大動脈センサーとは、血液中の二酸化炭素量を感知して、
一定量になると呼吸中枢に「酸素をください」シグナルを送る。
ジャンクフード、精白穀物、砂糖などの大量の糖を
メインエネルギーにしているのでは細胞は
酸素をうまく取り込めていない。
(糖質は代謝に酸素を必要とせず、
二酸化炭素は脂質を代謝した時の最終産物)。
これが呼吸が浅くなる理由であると解釈している。
以下は自分に対する問いとして、
ジャンクフードや白米はほとんど食べていなかったのに
なぜさまざま症状がでていたのか?
答えは個人的に糖全般に対して脆弱であった。
これがいまのところの仮説的回答、つまり個人差である。
糖質制限の問題点にも言及しなくてはならない。
糖質制限ではタンパク質、油の割合が必然的に増えるが、
加工食品に偏る傾向がある。
理論的背景、問題点など整理しながら、
治療室の病者さんもすすめているが、
すでに糖に対して脆弱である一部の精神疾患、
アレルギー、感染症に対する症例がでているので、
これからも研究しながら現場に応用していきたい。
さて、4年間に及ぶ実験の過程で「息と食」の相互の関係、
それが「想念(メンタル)」と「動(からだの歪み)」
にまで影響を及ぼしている可能性があることへの
あらたな問いと回答のヒントにも気がついた。
今回、ケトン体まで言及できなかったが、
今後もブログ等で発信しているので関心のある方は
アクセスしてください。
タンパク質、脂質を使うミトコンドリア系の
2つの作り出す仕組みがある。
ジャンクフード、精白穀物、砂糖などの大量摂取は、
ミトコンドリアでのエネルギー産生が十分行われず、
代謝産物の二酸化炭素を感知する大動脈センサーが作動しない。
大動脈センサーとは、血液中の二酸化炭素量を感知して、
一定量になると呼吸中枢に「酸素をください」シグナルを送る。
ジャンクフード、精白穀物、砂糖などの大量の糖を
メインエネルギーにしているのでは細胞は
酸素をうまく取り込めていない。
(糖質は代謝に酸素を必要とせず、
二酸化炭素は脂質を代謝した時の最終産物)。
これが呼吸が浅くなる理由であると解釈している。
以下は自分に対する問いとして、
ジャンクフードや白米はほとんど食べていなかったのに
なぜさまざま症状がでていたのか?
答えは個人的に糖全般に対して脆弱であった。
これがいまのところの仮説的回答、つまり個人差である。
糖質制限の問題点にも言及しなくてはならない。
糖質制限ではタンパク質、油の割合が必然的に増えるが、
加工食品に偏る傾向がある。
理論的背景、問題点など整理しながら、
治療室の病者さんもすすめているが、
すでに糖に対して脆弱である一部の精神疾患、
アレルギー、感染症に対する症例がでているので、
これからも研究しながら現場に応用していきたい。
さて、4年間に及ぶ実験の過程で「息と食」の相互の関係、
それが「想念(メンタル)」と「動(からだの歪み)」
にまで影響を及ぼしている可能性があることへの
あらたな問いと回答のヒントにも気がついた。
今回、ケトン体まで言及できなかったが、
今後もブログ等で発信しているので関心のある方は
アクセスしてください。
2023/06/06
今から約10年前、糖質制限という言葉を
糖尿病の方から始めて聞いた。
当時は内容を理解しないまま、あまり極端なことは
やらない方が良いですよ、と自分が知らない領域とはいえ、
随分適当に答えてしまっていた。
あれから10年後の現在、1日の糖質を約50g前後に制限した食事を
実験的に実施してすでに5年目になる。
きっかけは、先ず家族の小麦アレルギーから始まる。
つれあいはパン好きでパンは自前で焼く生活を30年続けていた。
3年前のある日、眼の周辺が赤く腫れている。
調べてみると小麦粉が負担になっていたので、
すぐに小麦粉を排除した食生活に切り替え数日で問題は解決。
以降、我が家では小麦は食することはほとんどなくなった。
ところがグルテンフリーに付き合っていた自分にも
隠れ鼻炎が良くなっているなど体調の変化に気が付く。
以前からヒトの病気の歴史に関心があって、
食の視点は大きなヒントになると考えていた。
二足歩行になって森を出た時、狩猟採集から農耕への変化など
人類誕生後700万年の間にヒトの食は大きく変化している。
いまさら狩猟採集の生活などは不可能であるが、
グルテンフリーをきっかけに糖質を制限すると
人体はどのように変化するのか?試してみることにした。
穀物は少量の酵素玄米、タンパク質は納豆、豆腐などの豆類、
魚、たまご、とり肉、油はナタネ油、オリーブオイル、
そしてできるだけ自家菜園の野菜。
生理、解剖の本をおさらいのつもりで読み始めてみると、
実は知らないことが多く、肝臓での糖新生など理解不足を痛感。
この食事法を実践して気づきの1つは深い呼吸になっていたこと。
これは冒頭で触れた隠れ鼻炎の解消にも関連するが、
むしろ細胞呼吸との関係だろう。
他には夏の猛暑の中でも体が楽に動き、
喉の乾きに常温の水が心地よかった。
さらに白眼の赤みが消えている、
歯茎がしっかりしているなど慢性炎症の細かい改善点は多々ある。
〜次回に続く〜
糖尿病の方から始めて聞いた。
当時は内容を理解しないまま、あまり極端なことは
やらない方が良いですよ、と自分が知らない領域とはいえ、
随分適当に答えてしまっていた。
あれから10年後の現在、1日の糖質を約50g前後に制限した食事を
実験的に実施してすでに5年目になる。
きっかけは、先ず家族の小麦アレルギーから始まる。
つれあいはパン好きでパンは自前で焼く生活を30年続けていた。
3年前のある日、眼の周辺が赤く腫れている。
調べてみると小麦粉が負担になっていたので、
すぐに小麦粉を排除した食生活に切り替え数日で問題は解決。
以降、我が家では小麦は食することはほとんどなくなった。
ところがグルテンフリーに付き合っていた自分にも
隠れ鼻炎が良くなっているなど体調の変化に気が付く。
以前からヒトの病気の歴史に関心があって、
食の視点は大きなヒントになると考えていた。
二足歩行になって森を出た時、狩猟採集から農耕への変化など
人類誕生後700万年の間にヒトの食は大きく変化している。
いまさら狩猟採集の生活などは不可能であるが、
グルテンフリーをきっかけに糖質を制限すると
人体はどのように変化するのか?試してみることにした。
穀物は少量の酵素玄米、タンパク質は納豆、豆腐などの豆類、
魚、たまご、とり肉、油はナタネ油、オリーブオイル、
そしてできるだけ自家菜園の野菜。
生理、解剖の本をおさらいのつもりで読み始めてみると、
実は知らないことが多く、肝臓での糖新生など理解不足を痛感。
この食事法を実践して気づきの1つは深い呼吸になっていたこと。
これは冒頭で触れた隠れ鼻炎の解消にも関連するが、
むしろ細胞呼吸との関係だろう。
他には夏の猛暑の中でも体が楽に動き、
喉の乾きに常温の水が心地よかった。
さらに白眼の赤みが消えている、
歯茎がしっかりしているなど慢性炎症の細かい改善点は多々ある。
〜次回に続く〜
2023/06/03
快ラボ・ふくしま 協賛のお願い
快ラボ・ふくしまの趣旨:
東日本大震災・原発事故後から今年で12年目を迎えます。大きな災害では正確な情報と対処の智慧、それらを共有するコミュニティの存在が大切になります。これからも快医学普及活動、コミュニティーサロン事業などを通して助け合いのセーフティネットの構築を目指しますが、「快ラボ・ふくしま」はその活動の一翼を担う位置付けとして企画しました。協賛金は快ラボ運営費として大切に使わせていただきます。どうぞ、ご協力お願いいたします。
具体的に「快ラボ・ふくしま」は4つの柱があります。
・快医学入門講座
・保養相談会
県内外から保養実施団体が集結して夏の保養説明会になります。コロナ禍で途絶えていた保養活動を活性化させる意味からとても重要な企画。
・「かくれキニシタン」上映
保養の必要性と「今の福島」をリアルに映し出す
・「快ラボ・マルシェ」、飲食や雑貨等来場者誰にでも楽しんでもらえるお店。
快ラボふくしまのコンセプトは「新たな出会い」。
このイベントを通して多くの方々にご来場いただき、
今の福島を語り、交流しましょう。
快ラボ・実行委員会 橋本俊彦
松本市岡田町793-3
0263-75-8608
メール:hashi22jan@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
協賛金
お振込先:
一口:1000円(何口でも可)
大東銀行(0514) 深沢支店(039)
普通 3003129
こおりやま子育ちの会
代表 猪股美奈
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
快ラボ・ふくしまの趣旨:
東日本大震災・原発事故後から今年で12年目を迎えます。大きな災害では正確な情報と対処の智慧、それらを共有するコミュニティの存在が大切になります。これからも快医学普及活動、コミュニティーサロン事業などを通して助け合いのセーフティネットの構築を目指しますが、「快ラボ・ふくしま」はその活動の一翼を担う位置付けとして企画しました。協賛金は快ラボ運営費として大切に使わせていただきます。どうぞ、ご協力お願いいたします。
具体的に「快ラボ・ふくしま」は4つの柱があります。
・快医学入門講座
・保養相談会
県内外から保養実施団体が集結して夏の保養説明会になります。コロナ禍で途絶えていた保養活動を活性化させる意味からとても重要な企画。
・「かくれキニシタン」上映
保養の必要性と「今の福島」をリアルに映し出す
・「快ラボ・マルシェ」、飲食や雑貨等来場者誰にでも楽しんでもらえるお店。
快ラボふくしまのコンセプトは「新たな出会い」。
このイベントを通して多くの方々にご来場いただき、
今の福島を語り、交流しましょう。
快ラボ・実行委員会 橋本俊彦
松本市岡田町793-3
0263-75-8608
メール:hashi22jan@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
協賛金
お振込先:
一口:1000円(何口でも可)
大東銀行(0514) 深沢支店(039)
普通 3003129
こおりやま子育ちの会
代表 猪股美奈
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・